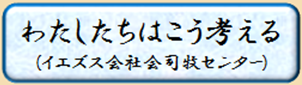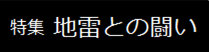日本では、年間3万人以上が自殺している。日本では、死刑判決がこの10年で2~3倍に増えている。日本では昨年、臓器移植法案が改正され、脳死臓器移植が可能になったが、国民の間でまだまだ議論が分かれている。
日本では、年間3万人以上が自殺している。日本では、死刑判決がこの10年で2~3倍に増えている。日本では昨年、臓器移植法案が改正され、脳死臓器移植が可能になったが、国民の間でまだまだ議論が分かれている。
これらはいずれも、私がイエズス会社会司牧センターの仕事を通して取り組んできたテーマだが、そこに共通している一つの問題は、「日本人の死生観」-と いうよりも「死生観の欠如」だ。自分の死についてのイメージがあいまいだから、簡単に(ではないのだろうが)自殺してしまう。他人の死についてのイメージ が漠然としているから、簡単に死刑にしてしまう。そもそも、人の死についての考え方があいまいだから、「脳死」についての議論が堂々巡りになってしまう。
そもそも人の死とは何なのか。生物としての死と社会的・文化的死の違いは何か。宗教は死をどう考えるのか。なぜ、現代人は死を受け入れられないのか-このように、死についてさまざまな角度から考えたのが、本書『死を忘れた日本人』だ。
著者は東京大学病院でがんの放射線治療と苦痛緩和ケアを専門にして、2万人近いガン患者の治療に関わってきた医師だ。年齢は私と同じ50歳。宗教は特に 信じていないようだ。だから、著者の言っていることは、深遠な哲学でもなければ、神秘的な教えでもない。科学者として、そして医師として、理性的で分かり やすい文章で、死について語る。
著者自身がまとめる本書の内容は、こうだ。人間は必ず死ぬ。宇宙でさえ死を迎える。絶対時間と生物時間は違う。人間一人ひとりにとっても、時間の流れ方は違う。
生物が無性生殖から有性生殖へと進化して、個体の多様性を獲得するのと引き換えに、個体の死も生まれた。
人間は脳を発達させることで、自分の死を認識するようになった。死の恐怖から逃れるために、宗教を発達させた。死はよく分からないから恐ろしい。葬儀や墓のことまで含めて、死について学べば、恐怖は減る。生命の始まりと死の定義は、天から降ってくるものではなく、自分の意志や宗教的信念、共同体の合意によって定められるもの。がんによる死は「予見される死」。死を迎える準備をすることは、残された人々への思いやり。年齢とともに成熟すれば、死を受け入れやすくなる。いたずらに死を恐れることなく、ありのままに死と向き合うことが大切。
当たり前と言えば、当たり前のことばかりだ。著者は医師ではあるが、取り立てて難しい資料を使って議論しているわけではない。
「宇宙が死ぬ」というのも、ずいぶん前から常識となっている。「生物時間」という考え方も、たとえば『ゾウの時間 ネズミの時間』という本で有名になった。つまり、ネズミの一生は2~3年、ゾウの一生は70年だが、心拍数(心臓の動く回数)で言えば15億回で一緒なのだ。「無性生殖」、つまりアメーバの ように細胞分裂で増える生物には、「個体」という概念もなく、従って「個体の死」もないとういうことも、学校で習っている。そして、古今東西の宗教が 「死」や「死後の世界」について語っているのも、常識だろう。私たちは「死」について十分な予備知識を持っているはずなのだ。
著者によれば、現代の日本人が死を必要以上に恐れるのは、宗教を失い、共同体の絆も弱くなって、死について考える機会がくなり、ひたすら生にしがみつこうとするからだ、という。だが、「死を考えることは、生を考えること」。死から目を背けて、「よく生きる」ことはできない。
私の両親も80歳に近づき、死の準備を進めている。子どもとしてはショックだが、受け止めなければならないことだ。決して割り切れることではないが、信仰者として、人間として、考えたい。
柴田 幸範(イエズス会社会司牧センター)