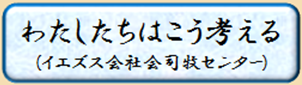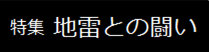おおた まさる
福音の小さい兄弟会
シャルル・ド・フコーは、20世紀初頭、トラピスト修道院の禁域生活を出て、イエスの生きたナザレトでの隠れた生活を召命として、観想的祈りの生活を普通の庶民の生活の中で実現させました。その多様な直観に光を当てるのに、「3世紀末のエジプト砂漠の師父の隠遁者の伝統」を再発見する点から伝記を書いて、20世紀初頭のフランス宗教界にブームを巻き起こしたルネ・バザンがいますが、2020年10月のフランシスコ教皇の『Fratelli Tutti』=皆の兄弟は、シャルル・ド・フコーの霊性に「一番見捨てられている兄弟姉妹との一致」の観点から光を当てています。アルジェリアのサハラ砂漠の中で禁域を伴う隠遁者生活から、脱皮して「世界から顧みられることも無かったトアレグ人の一人」となり、自己変革を怖れず「すべての人の兄弟」へと変容を遂げたシャルル・ド・フコーの霊性に、コロナ禍に打ち勝つ生き方を見だそうとフランシスコさんは提案をしているかのようです。

シャルル・ド・フコーは、サハラ砂漠の奥地に入り込むのに、フランス軍の前進基地を足場にしていましたから、アルジェリア政府としては、シャルル・ド・フコーは植民地拡張の先兵であり、なかなかその存在の意義を認めようとしませんでした。これには一理があり、16世紀スペインの宣教師たちの日本布教と同じ限界を彼の活動も持っていました。しかし、シャルル・ド・フコーの心意気は、植民地主義からは遥かに遠く、アフリカの一部族の人びとに溶け込んで、彼らの一人のようになって生活することでした。人類全体が免疫を獲得しなければ収まらないコロナ・パンデミックに向き合うためには、ワクチンの特許の権利を捨て去り、アメリカ人もアルジェリア人もどの小国の子供も、「すべての人の人権が尊重される人間にやさしい社会」だけがコロナ禍に打ち勝てるのですから、シャルル・ド・フコーの「みんなの兄弟になる」霊性は、今の私たち皆の緊急の課題でしょう。
彼の列聖に関わる象徴的なエピソードは、2020年5月にシャルル・ド・フコー列聖の決め手になった奇跡が、「un miracle de preservation=予防の奇跡」というもので、救われた青年がシャルル・ド・フコーを知らない、しかも信仰を持っていないという「隠れたナザレトの生活」を召命とする彼らしい奇跡だということです。具体的場面は、フコーの列聖を祈る祈祷会が行われていた教会の近くの工事現場で16メートルの高さから転落して即死のはずの青年が奇跡的に軽症で助かったという「予防の奇跡」です。僕は個人的には、列聖とか奇跡とかはあまり興味がなくて申し訳ないのですが、こういう神秘的でもなく日常生活にかかわる奇跡というのは好きです。すべての人の兄弟になるということも、すぐに出来ることではなく、自己変革・脱皮を怖れず、日常的に少しずつ積み上げていくものだと思います。
 思い返してみれば、30年以上前に東京生まれの自分が、小さい兄弟らしく、埼玉県秩父の安定した鉄工所仕事を辞めて、和歌山の被差別部落に2人の兄弟と共に引っ越してきて、皮なめしの仕事を始めたのも、日常生活での積み上げを通しての自己変革を求めたということだと思います。具体的に、部落解放運動で○○という成果を挙げた、とかの目覚ましいことは一切なく、生活レベルでの「あ、共箸でいいんだって。」と訪ねた家で、職場友達から台所の奥さんに言葉が伝わって行くようなことの繰り返しの中で、パン種が膨らんでいくような波長の伝播が何度も何度も起きれば良いと願っていました。
思い返してみれば、30年以上前に東京生まれの自分が、小さい兄弟らしく、埼玉県秩父の安定した鉄工所仕事を辞めて、和歌山の被差別部落に2人の兄弟と共に引っ越してきて、皮なめしの仕事を始めたのも、日常生活での積み上げを通しての自己変革を求めたということだと思います。具体的に、部落解放運動で○○という成果を挙げた、とかの目覚ましいことは一切なく、生活レベルでの「あ、共箸でいいんだって。」と訪ねた家で、職場友達から台所の奥さんに言葉が伝わって行くようなことの繰り返しの中で、パン種が膨らんでいくような波長の伝播が何度も何度も起きれば良いと願っていました。
皮革工場勤務の10年の内で、華々しいことと言えば、「部落解放基本法制定運動・全国行進」に和歌山県の分だけですがシスター橋本とガレロン神父との3人で参加したことくらいでしょうか。カトリック教会内部では、大阪教区の「カトリック部落差別と人権を考える信徒の会」でのアンケート3部作(信徒と司祭とシスターの差別意識調査)作りに参加したことは記憶に残ります。信徒の会での小教区教会への「出前」を私たちが繰り返す中で、本体の解放運動は1965年の「同和対策審議会答申」で部落問題の解決は国民的課題であると国に認めさせ、大きな前進を遂げました。日本全国で6000部落300万人の被差別部落民を率いて運動してきた解放同盟は最盛期の1986年には2300支部、同盟員18万人にまで浸透しました。
 江戸時代には、差別することが封建社会を守るために当然の義務だったのですが、明治以後の近代国家では、国家の統一のためには、国民の平等の権利が保障されなければならず、さらには1945年の敗戦後の日本国憲法では、個人の人権は侵すべからざる重みをもっています。
江戸時代には、差別することが封建社会を守るために当然の義務だったのですが、明治以後の近代国家では、国家の統一のためには、国民の平等の権利が保障されなければならず、さらには1945年の敗戦後の日本国憲法では、個人の人権は侵すべからざる重みをもっています。
しかしながら、コロナ禍の下、社会的少数者、社会的弱者、外国人労働者は、日本社会の持つ差別体質に直面し、声を挙げざるを得ない状態に追い込まれています。「すべての人の人権が尊重される人間にやさしい社会だけがコロナ禍に打ち勝てる」(ハンセン病市民学会の共同代表・和泉眞藏)のですから、フランシスコ教皇の「皆の兄弟」の精神、シャルル・ド・フコーの自己変革・脱皮の努力をテコにして、コロナ禍の日常を乗り切ってゆきたいものです。そして、具体的な日常の生活から立て直していきながら、社会的に問われているインターネット上の被害救済、「全国部落調査」復刻版の問題、さらには国際的に問題となっている「ラムザイヤー論文」の論破などにも注目していきたいと思います。
運動が国際化していく中で、構造的問題が出てきていることも付け加えておきます。つまり、外国人差別の底にある「労働力だけ輸入して、外国籍の人間には、家族は入国させない政策」が、部落差別の起源と言われる平安時代の「京の都の清掃労働問題」とそっくりだからです。都の疫病死者の遺体の片づけを河原者(かわらもの)に命じながら、住まいは強制的に都の外・洛外に追いやっていたのです。さらに付け加えれば、部落差別がいまだに無くならないのは、それによって利益を受けている人たちがいるからですが、この外国人差別についていえば、利益を受けているのは、私たち日本人です。差別を止め、家族の入国を許可し人間的な処遇をするには、国は予算を組み、私たち平均的国民は「無意識の異国人排斥心理」を改める必要があることを胸に刻みたいと思います。