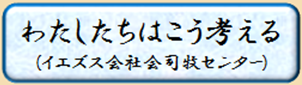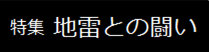栗田 隆子
文筆家
先日、プロテスタント系のクリスチャンのある知人とのやりとりで、何気ない質問をもらった。
「女性神父って世界標準で存在していないんですか?」
なるほど。例えばヨーロッパ大陸には存在するが日本にはいない、といった風に思われたのだろう。
「女性神父は世界に0人なんですよ。」
と私は答えた。先方はカトリックのことに無知で…と恐縮していたが、真に恐縮すべきはこちらだとつくづく思った。
そう、聖公会も女性司祭が存在している中で、「神父」という言葉通りカトリックに司祭職女性は存在しないのだ。
しかし私自身は今まで女性司祭がいないことにそれほど神経を尖らせてなかった。なぜなら私がいわゆる「小教区」のコミュニティで育ってきたというより、「修道院」の修道女(シスター)たちに影響を受けてきたし、修道院の存在がなければ洗礼を受けなかったと思われる信徒人生だったからである。いまだに神父の知り合いはあまりおらず、信徒の友人すらほぼほぼ女性である。
むしろ女性が教会を根っこからずっと支えてきているのに、司祭・司教といった「男性」だけが目立つことこそがまず問題であると感じていた。つまり「女性リーダー」がいないことも確かに問題だが、それ以上に問題なのは――いわゆるエッセンシャルワーカー・ケアワーカーの社会的評価が全くなされていない話と地続きだと思うのだが――、シスターや女性信徒が本当は教会内の細々したことを仕切ったり、キリスト教学や聖書学、または社会運動、あるいは霊的な歩みの蓄積を積み重ねながらも、神父・司教を前にすると一歩引いている状況に対して、とても不思議で理不尽な思いを漠然と抱いていたのである。
しかし私が本気で教会のジェンダーの問題に対峙しなければならないと思ったのは、教会内で起きた性虐待・性暴力の問題があったからである。性暴力や性虐待が起きたのみならず、その事実を組織ぐるみで隠蔽し、性虐待や性暴力を起こした司祭や司教等を、聖職者として「延命」させていたのだから、もはや組織的確信犯である。
私はその昔、ゆるしの秘跡で自分がいわゆる「付き合っている」相手との関係について語り、私の罪があれば認め赦しを乞いたいという話を
しかしのちにこのカトリック教会における性虐待・性暴力については聖職者の責任を追及するのみならず、まずもって私もまたきちんと反省をしなければならないとも感じた。というのも、この性虐待や性暴力の問題を2005年にイグナチオ教会でアメリカの事例を紹介されたのにもかかわらず、私自身何も動いてこなかったからである。
その理由は何の言い訳にもならないが、私自身が「神父」との付き合いがほとんどなく、どうしてそんなことになるのかがイメージできなかったというのもあったかもしれない。
そのような私がなぜこの教会の性暴力・性虐待を直視、そして対峙しようと考えたのかと言えば、皮肉にも「左翼」「労働運動」「フェミニズム」にも性差別やハラスメントなど社会構造の問題が存在していることを経験したからである。私自身はカトリック信徒でありながら(?)、労働運動やさらにフェミニズムの世界にもしっかりコミットしてきた。いわばキリスト教からは、身体や精神あるいは社会的な「脆弱さ」に対して祈りや聖書を通して向き合う意味を、社会運動やフェミニズムからは、社会的な脆弱さを抱える立場とみなされるものがいわゆる「物申し、行動する」力の意味を、それぞれ教えてもらい、どちらも重要で欠くことのできぬものだと考えていた。でも悪く言えば、それはいわばカトリック、そして社会運動やフェミニズムの「いいとこどり」だけをしようとしていたのかもしれない。
しかし、教会も社会運動も社会構造が生み出す「悪」にずぶずぶで、場合によってはこれらの組織や団体が率先してその悪を「実践」している現実が目の前にあった。その現実を目の当たりにし、もはや「いいとこどり」も「逃げ場」もないし、またそれらを「なかったこと」にもできなかった。
それならば、「カトリック教会」も「社会運動」そして「フェミニズム」に対してもどっしり構えてこれらの社会構造の悪にずぶずぶに浸っている現実そのものに自分ができうる限り対峙しようと決めたのである。
そしてこれらの組織、すなわちカトリック教会も社会運動もフェミニズムもある共通項がある。それは「きれいな言葉やかっこいい言葉をそれぞれ持っている」ということだ。カトリック教会ならば次々と発せられる愛や希望や信仰といった言葉が、社会運動ならば連帯や社会正義、フェミニズムならばエンパワーといった言葉である。しかしそれが本当に実現されているのか?あるいはそれらの言葉がキリスト教用語で言えば「受肉」されているのか?と問いたくなる現実がある。しかも怖いことにそれらのきれいな言葉こそがまた現実の直視を妨げがちなのである。
 四旬節の第二金曜日が「性虐待被害者のための祈りと償いの日」と定められたが、この日こそ大斎・小斎、灰を撒き散らし、服をバリバリ切り裂いて被害者の訴えを聞いて、神と被害者に謝らねばならないと思う。しかし日本のカトリック教会で起きている性虐待・性暴力に対して、今のところ日本の教会で真っ当な謝罪がなされているとは残念ながらいえないだろう。謝罪と償いが被害者になされているならば、少なくとも教区に対する訴訟は起きていないだろうし、被害者の会もできてないだろう…と思うが読者の皆様はいかが考えられるだろうか。
四旬節の第二金曜日が「性虐待被害者のための祈りと償いの日」と定められたが、この日こそ大斎・小斎、灰を撒き散らし、服をバリバリ切り裂いて被害者の訴えを聞いて、神と被害者に謝らねばならないと思う。しかし日本のカトリック教会で起きている性虐待・性暴力に対して、今のところ日本の教会で真っ当な謝罪がなされているとは残念ながらいえないだろう。謝罪と償いが被害者になされているならば、少なくとも教区に対する訴訟は起きていないだろうし、被害者の会もできてないだろう…と思うが読者の皆様はいかが考えられるだろうか。
おそらくこの問題は聖職者が中心の問題であるが、聖職者だけの問題ではない。それこそ信徒の一人一人が性虐待・性暴力被害者の言葉に耳を傾け、なすべきことをしてきたとは言えまい。私自身も今まで何もしてこなかったのだから、少なくともそれらの信徒を責める資格は私にはない。これはいわば私の恥と罪を語る論考でもある。
性虐待や性暴力は、子どもの頃であれば被害を受けたという認識すら困難な場合がありうる。また成人時に被害にあったとしてもPTSDなどの影響でその出来事を想起することさえ困難なこともある。それゆえ訴訟に数十年を要するケースもある。それでもなお声を上げるしかなかった現実の重みを想像できるだろうか。この現実をカトリック教会は直視すべきである。
ちなみに1998年に米国三菱のセクシュアル・ハラスメント訴訟はその補償金が3400万ドルで和解が成立した。この訴訟が世界的に企業内におけるセクハラ対策の変化の一つを促したと言われているが、日本の教会が裁判で多額の補償金を支払う羽目になれば少しは変わるのだろうか。少なくともそうなれば聖職者も私を含めた信徒も文字通り痛い目に遭うのは間違いないのだろうから。
追記
この原稿の提出後、2021年4月12日付の『クリスチャントゥデイ』のサイトに、「イエズス会神父がパワハラか、女性信者が適応障害に 日本管区が調査委設置」という見出しの記事が掲載された。「カトリック広島教区の40代の女性信者が、イエズス会所属の外国人神父からパワーハラスメントを受けたと訴え、イエズス会日本管区が調査委員会に当たる『ハラスメント防止対策委員会』を設置し、調査を行っている」といった内容である。
私はこの件の当事者を直接知っているわけでもなく、事の真偽をジャッジできる立場にはいない。だが、ハラスメントを指摘されたときに、頭ごなしに否定しないことは重要だ。そして介入が必要であれば第三者をどのような基準で選び、どのような介入が望ましいかを当事者・周囲の人間ともども模索する必要がある。そもそも私がこの出来事を「なかった」かのようにスルーするのはこの原稿の内容と著しく矛盾する行為である。ハラスメントの訴えがあったときに、被害を訴えた人に誠実に対応すること、解決とは何かを考えること、それは事件の直接の関係者ではない人間も日々考えるべきことではないだろうか。ハラスメントは他人事ではない。神父含む聖職者、信徒それぞれがいつでもハラスメントの加害者・被害者になりうるのだ。「恐れ」や面倒を避けたいがためにハラスメントの問題から目を背けるのはやめよう。教会外の「困っている人」を助けるのもいいが、足元の訴えにまずは耳を傾けるべきである。