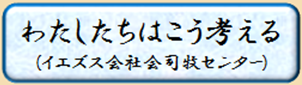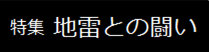遠藤 抱一
学校法人アジア学院副理事長、カトリック藤沢教会所属
栃木県の県北、那須塩原市(旧西那須野町)に、15か国ほどの人々から成る約60人の小さな共同体があります。アジア学院と呼ばれる途上国の農村開発指導者の養成を目指している学校です。有機農業によって自ら米や麦を作り、野菜を育て、豚や鶏を飼い、自給自足の生活の中から、途上国の農村の人々と共に生きるために必要な心と知識・技術の習得に励んでいる学生、教職員、そしてその研修を助けるボランティアたちの共同体です。

小史
アジア学院(以下学院)という法人名からだけではどんな教育をしているのかよく分かりませんが、学校名のアジア農村指導者養成専門学校と聞けば、その事業内容の見当が付くかと思います。学院は、前身が日本基督教団の農村伝道神学校(農伝・町田市)内の一コースであったため、プロテスタントの日本基督教団の関係学校となっています。農伝時代(1960年~1972年)には、学生は東南アジアからのみでしたが、1973年の学院創立数年後には世界中の開発途上国に門を開き、近年はアジアのみならずアフリカ出身者が増えています。
事業内容
農村開発指導者研修は開発指導者の養成で、単に農業技術の習得を目指すものではありません。サーバントリーダーシップなどの指導者論、環境と開発を考える開発論など座学を教室で学び、米・小麦や60種を超える野菜栽培の有機農業や豚・山羊・鶏・養魚の畜産等持続可能な農業及び技術を農場で実習します。また共同体の形成に関わる理解と実践も、学院のモットーである「共に生きる」を実現する大切な内容の一つです。約2週間に亘る熊本県水俣に至るまでのマイクロバスによる西日本研修旅行等も毎年秋に行われ、1年分のカリキュラムを、長期休暇抜きに4月から12月までの9か月に圧縮して実施します。
しかしより学院らしい特長は、こうした学校側が計画した教務内容以外に、学生は時間と場所を選ばず互いに学び合うのです。その一例を挙げれば、ある時の人参の作付けに関する授業の時でした。一人のスリランカの学生が、授業の最後に手を上げ、「先生、圃場の整え方や有機肥料の使い方はよく分かりました。しかし問題があります。象です。漸く収穫を迎える頃になると、必ず象の群れが来て、収穫物を食べてしまうのです。人参も例外ではありません。どうしたら防げますか?」 これには、教壇に立っていた教師も答えようがありませんでした。するとあるアフリカの学生が手を上げ、「自分の国では象の被害を防ぐため、作物を植えた畑の周りに、ゴマを植えている。試してみたらどうだ」と言ったのでした。なぜなら人参とともにゴマも生長し、収穫時期までにはちょうど象の腹に届く高さになる。象は腹が弱点だから、腹に当たるものがあると侵入しないとの説明でした。学生はそれぞれが、その土地の充分な農業経験者で、途上国農村の古来からの知恵を身に着けているのです。こうして学生は、新しい科学的な知識・技術を学ぶことに加え、互いの土地にある古来の農業の知恵をも学ぶのです。学院は、学校としてだけではなく学び合う共同体としての価値がその半分なのです。

経営
学院では留学生やその所属のNGOから学費を取りません。自らの研修の場である農場の生産物や畜産物による自給自足を実現し、また学院構内の各学生寮で共同体生活をしていますので、生活費も限られた額で済みます。しかし学生一人に要する年間の養成費用は400万円を超えます。年間予算の4分の1程度は、農場の生産物や短期セミナーの開催など学院の持つ生産力やノウハウから得られますが、不足分は国内の個人や社会奉仕団体・財団・教会に加え、先進国世界のキリスト教系の支援団体による奨学金や寄付金・助成金により支えられています。
学生(パティシパント)
学院で農村開発指導者研修に参加しているのは、原則アジア、アフリカ、オセアニア、中南米等開発途上国で農村開発事業に携わっている現地NGOの専従者です。日本人で青年海外協力隊志望者や途上国での農村開発事業に関心のある若者などの数名を加え、毎年ほぼ30名を受け入れます。学院ではパティシパントと呼ぶ海外からの学生は、既に農村開発の現場経験を数年有することが必須で、50才未満の、また途上国女性の社会経済的地位向上を願って、毎年女性の参加も重視しています。平均年令は35才前後、ほぼ半数は既婚者です。牧師も一定数いますが、神父やシスターも入学します。スリランカからお坊さんが来たこともあります。研修修了後は元の職場に復帰するのが原 則です。授業と日常生活の共通語は、途上国の中で最も広く使われている英語を採用しています。
入学希望者が個人として学院に入学願書を出すことは出来ません。所属しているNGOの推薦が選考の条件です。学院では、本人以上にそのNGOの活動内容や実績を重視します。今ではそのための調査活動を、全世界58か国に居る1,400人を超える卒業生が支えてくれます。これだけの調査能力と途上国の開発現場に通じていることは、学院の特長の一つです。
職員とボランティア
教職員数は、嘱託やパートも入れて約25名です。学生募集等を担当する教務課、フードライフ課は有機農業や畜産、給食を担当、募金や農場生産品を扱う国内事業・募金課、共同体生活をより豊かに送るためチャプレンも置かれています。教員の多くが海外での農村開発援助事業の経験があり、国籍も5か国以上に及び、卒業生も複数います。
また毎年国内及び海外先進国からの幅広い年齢層の男女10名を超えるボランティアが、1年の長期間共同体に加わり、農場、食堂、学生寮、事務室などで学生の研修や学院の運営を補助し、更に共同体の多様性を豊かにします。また短期や通いのボランティアも毎年多数受け入れています。
宗教
学院の依って立つ背景はキリスト教ですが、学生の宗教的背景は問いません。学院は新旧を問わずキリスト教会のネットワークに強みがありますので、学生の多数派はおのずと様々な教派のキリスト教徒になりますが、毎年数名のモスレム、ヒンズー、仏教徒など他宗教の学生も受け入れます。食堂はそれぞれの宗教に合った食材の調理に対応しますし、例えばイスラム教徒がラマダンの時期に入れば、その飲食の時刻にも配慮します。
学期の当初は、異なる宗教に互いに違和感を抱いたり戸惑うこともありますが、時が経つにつれそれぞれの信仰を認め合うようになります。このことが、特に北米やヨーロッパの海外のキリスト教支援団体から、エキュメニカルを超え異なる宗教、いわばインターレリージャスの学院コミュニティが、小規模ながら平和的共存を実現していることに、世界の分裂ではなく融和への期待を持たせる試みとして特に注目・評価されている点ではないのかと思っています。この点で学院が、日本という立地を得たのは偶然ではないとも感じています。ヒンズーやイスラム、キリスト教等宗教色の強い社会の中では、学院のような存在が許容されるのは極めて困難ではないかと感じます。特定の宗教に特に強い否定的反応を示さない、寛容或いはある意味宗教に強い関心を持たない国民性が、キリスト教を標榜し且つ他の宗教も受容する学院の存在を許して来たとも思います。

学院の創立当初からのモットーは、「共に生きる」です。私たちはまた、フードライフという言葉を造りました。フード(食べもの)とライフ(命)は本来分けられないものと考えたからです。食べ物を作ることは命を守ることだから、食べものを持続可能的に作る方法を学ぶことは、共に生き、「すべてのいのちを守るため」につながると思うのです。
『社会司牧通信』第214号(2020.10.15)掲載