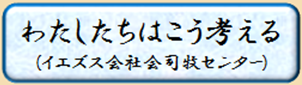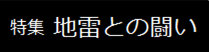―慈悲:愛(アガペ)の溢れとしての正義と平和―
小暮 康久 SJ
イエズス会霊性センター「せせらぎ」司祭
霊性と正義と平和との間にはいったいどんな関係があるというのでしょうか。今、私が感じていることを分かち合わせていただきたいと思います。
テーマとして霊性、正義、平和という三つの言葉を受け取ったとき、私の心にはじめに浮かんできたのは、下記に紹介するティク・ナット・ハンの一つの詩でした。
「あなたへの提案」
ティク・ナット・ハン 島田啓介訳
私と約束してほしい
今日 いまここで
太陽が天頂にあり
あなたの頭上にさしかかるいま
約束してほしい
あの者たちが
渾身の憎しみと暴力で
あなたを打ち倒し
踏みつけ
虫けらのように踏みつぶしても
あなたの手足を引きちぎり
腹を引き裂いても
忘れるな 友よ
憶えておくのだ
本当の敵は人間ではない
慈悲の行いのみが あなたにふさわしい
揺るがず 限りなく 無条件の慈悲こそが
憎しみの眼には 人に巣食う獣の心が見抜けない
きっといつか あなたは見据える
ひとりきりで 自分の中の獣を
決然とした勇気と
 慈しみと迷いのない眼で
慈しみと迷いのない眼で
(だれも知らないそのときに)
あなたの微笑みから
一輪の花がほころぶ
そのとき
あなたを愛するすべてのものが
生死を超えた三千世界から
あなたを見守るだろう
ひとりになった私は
ふたたび 頭を垂れつつ歩を進める
滅びぬ愛を胸にたたえて
果てのないでこぼこ道をゆく
太陽と月が
行く手をきっと照らしてくれるだろう
 ティク・ナット・ハン(1926–)は、仏教の瞑想法から始まった「マインドフルネス」を欧米に紹介したベトナムの僧侶として有名ですが、ベトナム戦争時に渡米し、キング牧師やトーマス・マートンと共にアメリカに広がりつつあった平和運動に大きな影響を与えた「行動する仏教」運動の創始者でもあります。ベトナム戦争の最中、祖国で人々が苦しむ様子を目にして、人里離れた僧院で修行を続けるべきなのかと自問したティク・ナット・ハンは、僧侶たちを連れ「山から降り」て、人々の救済のために尽くすことを決意します。民衆の救済活動と仏教修行とを同時に行う「行動する仏教(Engaged Buddhism)」の始まりです。
ティク・ナット・ハン(1926–)は、仏教の瞑想法から始まった「マインドフルネス」を欧米に紹介したベトナムの僧侶として有名ですが、ベトナム戦争時に渡米し、キング牧師やトーマス・マートンと共にアメリカに広がりつつあった平和運動に大きな影響を与えた「行動する仏教」運動の創始者でもあります。ベトナム戦争の最中、祖国で人々が苦しむ様子を目にして、人里離れた僧院で修行を続けるべきなのかと自問したティク・ナット・ハンは、僧侶たちを連れ「山から降り」て、人々の救済のために尽くすことを決意します。民衆の救済活動と仏教修行とを同時に行う「行動する仏教(Engaged Buddhism)」の始まりです。
この詩については、ティク・ナット・ハン自身が下記のように記しています。
「この詩を書いたのは1965年のこと、社会奉仕青年団(SYSS)の若者たちのためだった。戦争当時、日々いのちをかけて活動する彼らに、私は、憎しみを持たずに死を覚悟することを伝えようとした。すでに暴力によって殺された仲間もいたが、私は憎しみに負けぬよう忠告した。本当の敵は、自分自身の怒り、憎しみ、貪欲さ、狂信、他者への差別意識である。暴力によって殺されるなら、自分を殺す相手を赦すために慈悲の瞑想をすべきだ。慈悲を自覚しながら死ぬなら、人は目覚めた存在(ブッダ)の真の後継者となる。…心に慈悲をたたえて死ぬ者は、私たちの道を照らす松明となる。」
ティク・ナット・ハンの原点は、まぎれもなく、第二次世界大戦、インドシナ戦争、ベトナム戦争へと至った20世紀のベトナムが辿った過酷な戦争体験にあります。そこには、私たちが体験したことのないような怒りや憎しみ、恐怖が渦巻く状況があったはずです。この過酷な状況の中で、自らの内側からも湧き上がる怒りや憎しみを見つめ続けていたのは、ティク・ナット・ハン自身でしょう。「自分を殺す相手を赦すために慈悲の瞑想をすべき」という彼の言葉は、まさに自らも苦しみのうちに生き続けた言葉でもあります。次々に殺されていく師や仲間、若者たち、湧き上がる怒りや深い絶望。彼はひたすら歩く瞑想や座る瞑想を続け、じっと怒りの炎を抱きしめていました。
ある時、アメリカの北爆によってある村が全滅した時のこと、米軍の指揮官が「私は、その村を破壊しなければならなかったのだ。その村を共産主義から守るために」と新聞で語っているのを目にしたティク・ナット・ハンは激しい怒りを感じます。しかし、彼はブッダの弟子としての自分自身に立ち帰り、その激しい怒りを否定するのではなく、抱きしめ続けたのです。そしてついにその指揮官(加害者)たちへの慈悲を感じるようになるのです。「彼らは、“村を守る”といいながら、村の人を殺してしまった。しかしそれは彼らが『間違った認識の犠牲者』だからです。傷つけられた人たちと人を殺(あや)めることを命じられた兵士、共に怒りや憎しみ、欲望が生んだ戦争の犠牲者です。」こうしてティク・ナット・ハンは自分と他者の区別を越える慈悲の境地に至ります。すべてのものは繋がり合って、 支え合って存在している。インタービーイング(Interbeing:相互存在)という自分と他者の区別を越える慈悲の境地です。
このインタービーイング(Interbeing:相互存在)という自分と他者の区別を越える慈悲の境地とは、キリスト教でいうところの愛(アガペ)の境地でしょう。「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」というあの箇所(マタイ福音書の山上の説教部分の5:21–48の反対命題と呼ばれる箇所)は、まさにこの慈悲:愛(アガペ)の境地からの眺めであり、自分の立場(エゴ:自己中心)から見た「善い」と「悪い」を区別する場所からは決して見えてくることはありません。
この自分の立場(エゴ:自己中心)から見た「善い」と「悪い」を区別する場所は、キリスト教で言うところの「罪(ヘブライ語でハター:的外れ)」の現実と関係しています。創世記の中で神が「食べると必ず死んでしまう」と言ったあの「善悪の知識の木の実」を食べた私たち、神の似姿として創造された私たちの中にあるもう一つの現実です。「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈る」ことは、自分の立場(エゴ:自己中心)から見た「善い」と「悪い」を区別する場所からの自力だけでは決して実現することはできません。そしてそこから眺める「正義」と「平和」も自分の立場(エゴ:自己中心)によって歪んでいます。その意味で、反対命題と呼ばれる箇所は、私たちを自分の立場(エゴ:自己中心)から解放し、慈悲:愛(アガペ)の境地へと招く「窓」のような役割をもっているようです。
キリスト教の愛(アガペ)も仏教の慈悲も、「概念」や「主義」ではありません。恩寵(他力)とこの私の自由な応答(自力)が一つになったときに開かれてゆく、現成する「場」であり、慈悲:愛(アガペ)だけが溢れている「場」であり、本来の私がそこに在る「場」であり、真の現実です。
ヘブライ語の「平和」はシャロームですが、このシャロームの原義は「まったく欠けたところがない、満ち満ちた状態、球体のようなイメージをもつもの」です。つまり聖書が語る「平和:シャローム」において満ち満ちているものとは慈悲:愛(アガペ)であり、その慈悲:愛(アガペ)が満ち満ちた状態が「平和」ということなのでしょう。
教皇フランシスコも、2016年2月3日の一般謁見演説「いつくしみと正義」の中で、真の正義を成就させるのは神のいつくしみにほかならないと語っています。法に従って正義を行ったとしても、そこでは加害者と被害者を区別し、加害者を刑罰に処するだけで、それは因果応報の正義であり、悪を打ち負かすのではなく、抑制するだけであり、真の正義には至らないと。たとえそれが困難な道のりであったとしても、被害者がゆるし、加害者の幸せと救いを望むことによって、加害者が自分の悪行を認め、それを止め、善への道を再び見いだすよう助けられることにより、その不正義の人が正義の人になっていくことにこそ、真の正義と神のいつくしみの実現があると。
 結局、「霊性」とは概念や主義ではなく、慈悲:愛(アガペ)の境地という私たちの存在の深みに実質的に繋がっていく(ぶどうの木に繋がる)ことであり、その深みからの溢れとして、本物の(神の)「正義」や「平和」を知る(体験する)ということなのでしょう。そしてその本物の「正義」と「平和」だけが、私たちの真の幸いと関係するものなのでしょう。慈悲:愛(アガペ)のないところには、人と人の間にも、人と被造物の間にも真の幸いは実現しないでしょう。なぜならすべてのものは繋がり合って、支え合って存在しているからです―インタービーイング(Interbeing:相互存在)。この人間の世界に格差や紛争が絶えないことと、被造物たちが壊れていくことはまったく一つの現象なのでしょう。今こそ、私たちの存在の深み―慈悲:愛(アガペ)に実質的に繋がっていく霊性が目覚める時なのだと思います。
結局、「霊性」とは概念や主義ではなく、慈悲:愛(アガペ)の境地という私たちの存在の深みに実質的に繋がっていく(ぶどうの木に繋がる)ことであり、その深みからの溢れとして、本物の(神の)「正義」や「平和」を知る(体験する)ということなのでしょう。そしてその本物の「正義」と「平和」だけが、私たちの真の幸いと関係するものなのでしょう。慈悲:愛(アガペ)のないところには、人と人の間にも、人と被造物の間にも真の幸いは実現しないでしょう。なぜならすべてのものは繋がり合って、支え合って存在しているからです―インタービーイング(Interbeing:相互存在)。この人間の世界に格差や紛争が絶えないことと、被造物たちが壊れていくことはまったく一つの現象なのでしょう。今こそ、私たちの存在の深み―慈悲:愛(アガペ)に実質的に繋がっていく霊性が目覚める時なのだと思います。
『社会司牧通信』第214号(2020.10.15)掲載