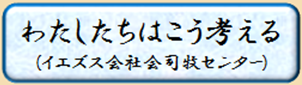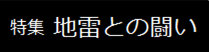小林 豊
カトリック青年
 38年ぶりに教皇が来日した。この来日は、間違いなく日本の教会にとって大きな喜びであったのだと思う。私の周囲でも滞在中にはSNSのニュースフィードが教皇フランシスコ一色になった。しかし、なぜ「いま」だったのだろうか。
38年ぶりに教皇が来日した。この来日は、間違いなく日本の教会にとって大きな喜びであったのだと思う。私の周囲でも滞在中にはSNSのニュースフィードが教皇フランシスコ一色になった。しかし、なぜ「いま」だったのだろうか。
前回の教皇来日時(1981年)、私の両親は20歳前後の若者であり、二人とも今の私よりも若かった。二人とも洗礼を受ける前で、当時の教会には若者が多かったことだろう。それに対して現在では、おそらくほとんどの教区や小教区において、司祭不足や信徒の高齢化が進み、もはや日本の教会が持続不可能であるとの危機感があるのではないだろうか。だが、はたしてこれは教会だけの問題だろうか。むしろ様々な面で社会全体が持続不可能な時代を私たちは生きていると言えるのではないか。
日本は一見平和で安全な社会である。しかし、その「平和」の影では、声を上げる力すら奪われた人々の呻きや叫びが常にこだましてきた。現代においても、至るところで嘆く価値のある“いのち”とそうでない“いのち”が選別され、多くの人々がその苦しみや死を認識される可能性すら奪われている。いじめや自殺、孤独死などはもはや珍しい出来事ではなく、なくならない差別や外国籍も含む弱い立場の労働者の使い捨てなど、弱くされた人々や貧しい人々に対する不正義がはびこっている。教皇来日のテーマが「すべてのいのちを守るために」とされた背景には、日本社会に対等な“いのち”のあり方を拒否するような価値観や構造が存在することが無関係ではないはずだ。
肥大化した市場原理があらゆる世界を飲み込み、“いのち”への畏敬が空虚な言葉に取って代わられ、恐ろしい勢いで人間の内と外に荒野が広がっている。その中で、若者たちは人間の本性を開花させる形ではなく、労働市場や社会の押し付ける枠組みの中での成功や自己実現を強要され、身も心も窒息させられている。子ども時代から偽りの言葉で薬漬けにされることで、「信じる」ことが奪われ、社会が生産性やスピードばかりを追い求めてゆく中で、生の喜びを味わう感性を養うための時間は嗜好品になりつつある。
教会は社会の中に存在する。現教皇は世界のどんな指導者よりも世界の現状に心を砕いてこられた。私が目にした彼の姿は、温かさや柔らかさ、静けさとともに、身体から滲み出る「哀しさ」も語っていた。そのような教皇だからこそ、その言葉は時に政治的な事柄を話しながらも、政治家のそれとは全く異なる色彩を帯びていたのだろう。
おそらく、今回の来日は「老いていく教会」に新しい炎を灯すためのものでもあったはずだ。私たちはその炎を胸に宿して「老いていく社会」で生きていかなければいけない。そして、その炎は、仮にあした日本が、もしくは世界が終わりを迎えるとしても“いのち”の尊厳のために働き続けるために必要な糧であり希望だ。
教皇の向こうに本当に生きた希望を「見た」気がする。彼の姿は、自らをそう紹介したようにこの世界をキリストと共に旅する「巡礼者」の姿だった。私もあの面影に励まされながら、この旅を続けたいと思う。