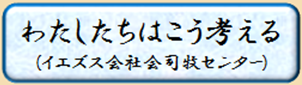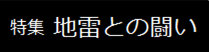~ハンセン病国賠訴訟熊本判決(2001年5月11日)から考える~
浜崎 眞実
カトリック司祭
「らい予防法」が憲法違反として断罪された2001年5月からは、ハンセン病に関するものの見方の枠組みが司法の場では大きく転換しました。しかし、それに他の分野が追いつけていないのが現状のようです。2019年6月28日には「ハンセン病家族訴訟」の原告勝訴の判決。その後控訴させず判決を確定させ、首相からの直接の謝罪を引き出すことができました。その結果を導き出したのは、家族訴訟の原告の声が大きな要因でしたが、それだけではなく2001年の熊本地裁勝訴判決の力が及んでいたからでもあるでしょう。
認識の枠組みの転換をもたらした2001年熊本地裁判決
私たちの国では「らい予防法」で合法的に、ハンセン病者とみなされた人を隔離して絶滅させ、国家をハンセン病から守るという「救らい」※活動が実践されてきました。それは善意の市民をも駆り立てるもので、優しい顔の慈善によって、ハンセン病者とされた者を社会から排除しました。人々が「救らい」活動へ促されていく背景には、「私たちの社会にはハンセン病に対して偏見差別が蔓延っている」との共通認識が前提としてあります。次に、そのような社会にいては迫害を受けるのではないかと心配します。更に、その危険を避けるために療養所に入り、そこで同病の仲間と一緒に生きる方が幸せであるとの決めつけに至ります。善意に溢れる思い込みが世間の常識になりました。
そのような社会にあって「らい予防法」による国策こそが憲法違反と認定したのが、2001年5月11日の熊本地裁判決でした。それは「天動説から地動説」、あるいは「天皇主権から国民主権」という動きにも匹敵する程の画期的な出来事でした。すなわちハンセン病問題※を見る枠組みの大きな転換が起きたのです。
問われているのは、個人の人格やアイデンティティではなく政治的権力的立場性
「誰もが忌避していたハンセン病療養所に、頻繁に訪問したのは宗教者だった」として「救らい」活動を誇りとし免責の根拠として語る宗教者もいます。しかし、熊本地裁判決によってものを見る枠組みの転換が起こったことを真摯に受け止め理解するなら、宗教者の「慰問布教」などの「救らい」活動は反省の対象です。それはハンセン病者と関わった個人のアイデンティティや人格を非難するのではなく、ポジショナリティとしての政治的権力的立場性が問われていることだからです。
それは2016年の「障害者差別解消法」で障害に対する認識の変更にも通じます。すなわち、障害が個人にあるとする「医療モデル」から、社会にこそ障害があるとする「社会モデル」への転換です。そこでは障害者への配慮が足りないから、障害者に対して優しく接しなくてはならないと主張しているのではありません。そもそもこの社会は「健常者」への配慮に満ちた「配慮が不平等な社会」なので、その配慮を平等にしようとの呼びかけです。それと同じことが2001年の原告勝訴判決によって起きたのです。原告の人たちは「困っているから助けてほしい」と裁判に訴えたのではなく、「らい予防法」は基本的人権の尊重を謳っている憲法に反していることを認めるようにと裁判を提起したのです。そのため、市民もこれまでの「救らい」という立場での応援団、支援者としての振る舞いでは連帯にならず、加害の継続になってしまいます。
さまざまなつながりで成り立っているのが私たちの社会です。そのつながりの中身を意識し振り返ると、「らい予防法」によって加害者に仕立て上げられた被害者であるのが私たち市民のポジショナリティ(政治的権力的立場性)に他なりません。そのポジショナリティから降りることで平等性が確保され、真の連帯も可能になります。非対称な関係で生きている市民が加害者に仕立て上げられてしまう現実が、ハンセン病問題によって映し出されている私たちの社会です。
優生思想に行き着く「救らい」活動
大日本帝国憲法から日本国憲法に変わり、教育勅語は廃止になりました。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という日本国憲法の趣旨に反するからです。それでも教育勅語の内容は素晴らしいと賞賛する人は今も存在します。親孝行や様々な徳目をあげて、人格形成に役立つなどとの理由です。同じように、「らい予防法」による国策が断罪された現在でも、「救らい」活動に問題を感じることなく、その考えを肯定する人もいます。ハンセン病者に献身的に尽くした人を誉め称えるという姿で今も出現します。しかし「救らい」活動とそのメンタリティとは決別しなくてはならないものです。「救らい」活動とは「らい予防法」の国策に対して、それに抗ってハンセン病者の人権を尊重する取り組みをしたのではなく、国の隔離政策と一体となって推し進められた活動だからです。それに対して「救らい」活動への反省もなく岩下壮一神父をはじめハンセン病者に尽くした人たちを讃えることは、教育勅語を今の時代でも活用することと同じではないでしょうか。
戦前に教育勅語は皇民化教育に活用され、戦争に向かう気運を高める役割を果たしました。それと同じように「救らい」活動はハンセン病者に対して救済と見せかけ、当事者が立ち上がるのをくじき、強制隔離政策遂行の補完的役割と隔離政策の実態を隠す機能を果たしてきました。要するに国家に迷惑をかけないように、迷惑になる人を無くす活動です。その行き着く先は、生活困窮者や疾病や障害のある人はいない方がいいという優生思想になります。
加害者の立場から降りることが差別の社会構造を除去する第一歩
今回の家族訴訟の判決※では、ハンセン病に対する差別は国によって作られ、個人の心の中というよりは、社会に存在していると判示しています。社会構造の問題です。いくら人格者で「聖人」と呼ばれるような人でも、この差別構造の中で生きざるを得ないので加害者になります。国策によって加害者に仕立て上げられているのです。したがって差別の構造を見抜き加害者としての政治的権力的立場にいることを認めることが差別構造を取り除く第一歩です。その上でハンセン病と共に生きてこられた人たちと関わり、加害者の立場から降りるのが課題となります。それは特権を放棄し、圧倒的に非対称な現実から脱け出すことです。すなわちハンセン病と共に生きてきた人たちを救済の客体とみなすのではなく、解放の主体であり協働する者として関わることです。そのためには「司祭と信徒」という非対称的な権力関係から離れることが必須でしょう。 第二バチカン公会議※が教会を「神の民」※と表現したことにも通じることです。聖書において、神との契約を交わした者は等しく尊いという基本的平等性を主張しているのが「神の民」だからです。それによって、聖職者と信徒という排除の境界線が取り除かれ、差別の社会構造をも除去していく取り組みもにも拓けることを願っています。
2001年の判決以降、国の啓発活動はポジショナリティには注意を払うことなく、心の工夫や道徳によって「善い人」や「こころ優しい人」になるように諭すアプローチでした(国立ハンセン病資料館の展示内容など)。そのような取り組みでは国策による人権侵害や差別構造を取り除く効果は出てきません。それはハンセン病療養所での断種や堕胎、そして嬰児殺の実行は、極悪非道な人物でなく、心優しく献身的ですらあった医師や看護師によって実施されていた事実からも窺い知ることができます。改めて私たちの社会と啓発のあり方が問われています。
間違いの否定ではなく間違いを共有する社会へ
しかし、人は自らが加害者であることを認めることは難しく、むしろ自己防衛機能を発動して、加害者であることを否定したり、それを見ないで済むように振る舞ったりするのも現実です。それは歴史認識問題を背景として、日本の戦争責任の問題や植民地政策の責任を認めたくないという姿勢にも通底します。2002年10月に拉致被害者が帰国し、世間は歓迎ムードでした。その頃、駿河療養所の自治会長の西村時夫さんは、「拉致被害者は羨ましい。日本に戻ってきたら、故郷の人たちが歓迎してくれる。私たちは日本という国家によって拉致されたようなもので、裁判に勝っても、未だに故郷の人たちから迎え入れられることはない…」と淋しく話していたのを思い出します。拉致問題では市民は被害者の側に立って、気持ちよく「応援団」として振る舞うことができます。しかし、ハンセン病問題では地域社会は国の隔離政策に追随して加害の立場に置かれました。そのため隔離された人たちを故郷に迎え入れることは、地域の人たちに加害者であることを突き付けることになるのです。すると加害者であることを認めざるを得なくなります。そのためハンセン病病歴者を故郷の人たちが迎え入れることは難しいという頑固で厳しい現実があるのでしょう。このような仕組みも踏まえて、加害者であることを認め、間違いを否定するのではなく間違いを共有する社会を作っていくことがハンセン病問題から問われていることです。カトリック教会はこれまで、間違わないことを標榜してきたので、間違いを断罪し否定するか、否認し間違いではないかのように振る舞う集団になっていたところがあるのではないでしょうか。ハンセン病問題に関する検証会議※の副座長であった内田博文さんは「加害者は、被害者から学び続けない限り、自分が加害者であることに気づかない」と言います。ハンセン病病歴者や家族の方々から学ぶことで、カトリック教会の間違いを否定するのではなく、間違いを間違いと認めそれを共有して、自らの加害性に目覚めることが肝心です。
《註》
※救らい: ハンセン病者を救済するようで、実際は国家をハンセン病から守ること。救らい活動では、救済される側と救済する側が固定化され、支配と被支配の暴力的な関係に陥る。
※ハンセン病問題: 国が作り出したハンセン病元患者とその家族への被害を、未だに私たちの社会は回復することができていないこと。「ハンセン病問題基本法(通称)」(2008年)で定義されている。
※家族訴訟判決内容: 戦前「周囲のほぼ全員によるハンセン病患者及びその家族に対する偏見差別が出現する一種の社会構造(社会システム)が築きあげられた。」この「社会構造に基づき、大多数の国民らがハンセン病患者家族に対し、ハンセン病患者家族であるという理由で、忌避感や排除意識を有し、ハンセン病患者家族に対する差別を行い(このような意識に反する意識を持つことは困難な状況になった)、これにより、ハンセン病患者家族は深刻な差別被害を受けたと認められる。」「この状況は、戦後、現憲法制定後も、無らい県運動を含むハンセン病隔離政策等によって維持され、ハンセン病患者家族に対する偏見差別も続き、人によっては強固になった。」(判決440−441頁)
※第二バチカン公会議: 1962−65年にかけて開催され、カトリック教会が方向転換を決定した会議。
※神の民: 聖書に立ち戻り、教会とは誰かを表現したもの。教会を位階制(ヒエラルキー)で捉えることなく、「いのちの神」との契約を背景に神の前では等しく尊いという基本的平等性を主張する表現。
※ハンセン病問題に関する検証会議: 2001年のハンセン病国賠訴訟判決に基づいて設置され、2005年3月に『ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書』を提出している。

《HP掲載にあたり、一部加筆修正しました》
日本植民地時代に韓国小鹿島(ソロクト)に
建てられたハンセン病施設の「救癩(らい)塔」
大天使ミカエルの像