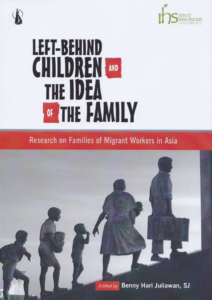移民のために働くイエズス会のこれから
ベニー ハリー ジュリアワンSJ
JCAP移民ネットワークコーディネーター

第36総会以降、イエズス会の中で「識別」という言葉が大流行しています。アルトゥーロ・ソーサ総長は、イエズス会における識別の過程と使徒的計画を審査するための特別顧問を任命しました。イエズス会東アジア・太平洋地域(JCAP)の移民ネットワークとしては、これまでの歩みを見直し、新たな進路を描くために、今年で第4回目となる年次会議を2017年3月23~26日に東京で行いましたが、それはふさわしいことでした。未来のための新しい計画が求められていたのです。
最も重要な議題は、過去3年間の光と影を考慮に入れたうえで、今後5年間の計画を立てることでした。いつになく寒い春でしたが、8つの移民機関から集まった14名の参加者の活気と議論が、イエズス会社会司牧センターを温めました。3人の神学生と、東京移民デスクの若いインターンも加わってくれました。
学習のためのハイライトと教訓
このネットワークは、2014年に、5か国の5つの独自の機関が、イエズス会のアイデンティティを共有していることから始まりました。したがって、最初のステップは、コミュニケーションと統治構造を確立することによって、より緊密な協力体制を築くことでした。メンバーはSkypeやGoogleドライブ、グループメールなどの最新技術をいち早く習得しました。数年間にわたって定期的にSkype会議を行い、年次会議も設けられました。そうした中で、2つの機関が新たに加わりました。
残っている主要な課題は、加盟機関が一般的に、能力としても資源としても非常に限られた小規模なものであるという事実です。特に人材に関しては、イエズス会からの貢献は、ほとんど変わっていません。けれども、韓国のユウッサリは例外です。この働きを重視する韓国管区の決定にしたがって、最近、金浦の2階建ての新しい建物に引っ越しました。この使命に伴い、新しいイエズス会共同体もまた、その近くに設立されました。
それぞれの違いにもかかわらず、移民労働者に関する共通の関心は、協働の中心的部分になりました。同伴と直接サービスの提供は、送り出し国でも受け入れ国でも、移民労働者のニーズに応える中核となりました。参加者は、研究を行う能力を築く必要性と、残された移民の子ども、再定住、ならびに仲介事業の問題について共同プロジェクトを組織する必要性を認識しました。これらの研究プロジェクトは、新しいスキルを教えるだけでなく、加盟機関の中に新たな熱意を生じさせ、彼らが自国の学者や政策立案者たちに働きかけるのを助けました。
ネットワークはまた、4年間にわたり、社会使徒職の枠を超えて移民に関する問題を促進することに努めました。非常に成功した戦略の一つは、JCAPが毎月発行しているニュースレターに記事を載せたことです。これらの記事のおかげで、多くの人々――イエズス会員ではない人も含めて――が、移民労働者に対するイエズス会の取り組みについて知るようになりました。さらに、神学生とブラザーの集まりが2016年にソウルであったとき、移民への関心がテーマとして取り上げられました。イエズス会大学連盟も、移民の現象にもっと注意を払うと約束してくれました。
次の5年間
今後数年間、ネットワークは「拡大」と「アドボカシー」という2つの領域に焦点を絞ります。
ネットワークは移民に焦点を当てた他の機関や地域のネットワークと協働する必要があります。それらのいくつかからはすでに、連携を求められています。司教協議会や教会の移民機関はとりわけ関連しています。香港、タイ、マレーシア、シンガポールなどの国では、イエズス会は移民センターをもっていません。けれども司教協議会や他の修道院が最前線で、移民の権利を推進し、人身取引と闘っています。
イエズス会難民サービス(JRS)との緊密な協働もまた、長期にわたっています。JRSアジア太平洋地区ディレクターのバンバン・シパユン神父は、教会の社会教説によって規定されている「事実上の難民」への派遣に、JRSも同じ関心を促進できるよう活用したいと強く願っています。この表現は、国際条約によっては通常は難民に分類されない、武力紛争、自然災害、経済失策の犠牲者のことを指しています。

この点に関して、JCAPはおそらく、別の地域からインスピレーションを得ることができるでしょう。ラテンアメリカとカリブ海地域のイエズス会移民ネットワーク(RJM-LAC)は、この地域の約83の機関を傘下に収めるグループです。2002年にいくつかの機関の緩やかな連携として始まり、その後様々な変化を繰り返しながら、2011年にRJM-LACとなりました。18か国から、JRS、社会センター、小教区、イエズス会の大学や学校などが集まっています。その中心課題は、中南米の様々な地域から北米に向かっている移民や難民と協力することです。この協働は、様々な種類の移民の間を厳密に区別することが必ずしも役に立たない、混ざり合った移民の流れがあるという現実を認識しています。
プログラムの面でも、アドボカシーに特別な注意を払う必要があります。移民労働者は使い捨て可能な労働力として、彼らの権利や尊厳はほとんど考慮されずに、必要な時にだけ雇われることは明らかです。2020年の東京オリンピックはまさにその典型です。日本政府は、より多くの外国人建設労働者が来るように法律を緩和していますが、社会的重大性に対処する用意ができていないか、対処する気がないようです。それに加えて、人権団体からは奴隷制に等しいと非難されている外国人技能実習制度もあります。
東南アジアに目を向けると、2015年にASEAN経済共同体が発足してもなお、家事労働や農園、建設業に数百万人の外国人労働者がいるということを認めるそぶりすらありません。加盟国は、2007年のASEAN宣言に伴い多くの部門から繰り返し呼びかけられたにもかかわらず、移民労働者とその家族を保護する手段に同意することができませんでした。その代わり、地域のグループは8つの部門に、いわゆるホワイトカラーの専門家に関する規定を設置しました。ネットワークは、各地で移民の権利のためのキャンペーンを開始し、経済的価値にのみ焦点を当てることなく、彼らの尊厳を促進するのに適しています。
一方、国連が2015年に採択した「持続可能な開発目標(SDGs)」は、政策変更を提唱するためのプラットフォームを提供しています。多国間のイニシアティブとして、国家間の対話のための国際的に認識できる話し方を提供しています。イニシアティブに掲げられている17の目標の多くは、移民労働者やその他の脆弱な移民に関するもので、出身国や在留資格にかかわらず、基本的サービスを含む社会的保護への権利を保障しています。経済成長に憑りつかれている中で、JCAP移民ネットワークを含む市民団体は、単なる経済開発だけでなく、人間中心の開発を強調すべきでしょう。
この計画は、アジア太平洋地域のイエズス会による、真剣な取り組みを必要とするでしょう。JCAPは、ネットワークの基盤を築くためのリソースを惜しみなく提供してきましたが、この計画を実現するためにはより多くのことを行わなければならず、より多くのリソースが必要となります。例えば、東京で行った今年の年次会議は、イエズス会日本管区の支援なしには実現できなかったでしょう。イエズス会にとって、このような寛大さは珍しいことではありませんが、現在の取り組みがより大きくなったときには、より一層歓迎されるでしょう。

シンポジウム
東京での会議は、ネットワークによる初の共同出版を記念したシンポジウムによって終了しました。『残された子どもたちと家族の概念』という本は、移民労働者の子どもたちの運命について、5か国でなされた研究の成果です。
その後、アジア太平洋地域における挑戦についての議論が続きました。主な挑戦は、現実には国境を越えた現象にどのように対処するかですが、私たちの働きの多くは現場で、あるいは性質によってもせいぜい全国のレベルです。ネットワークを構築することは、この限界を克服するための戦略です。それでもなお、能力と深い貢献を改善していく必要があります。東京での識別と計画は、今後数年間の新しい方向性を示すのにとても役立ちました。
Left-Behind Children and the Idea of the Family
booklet
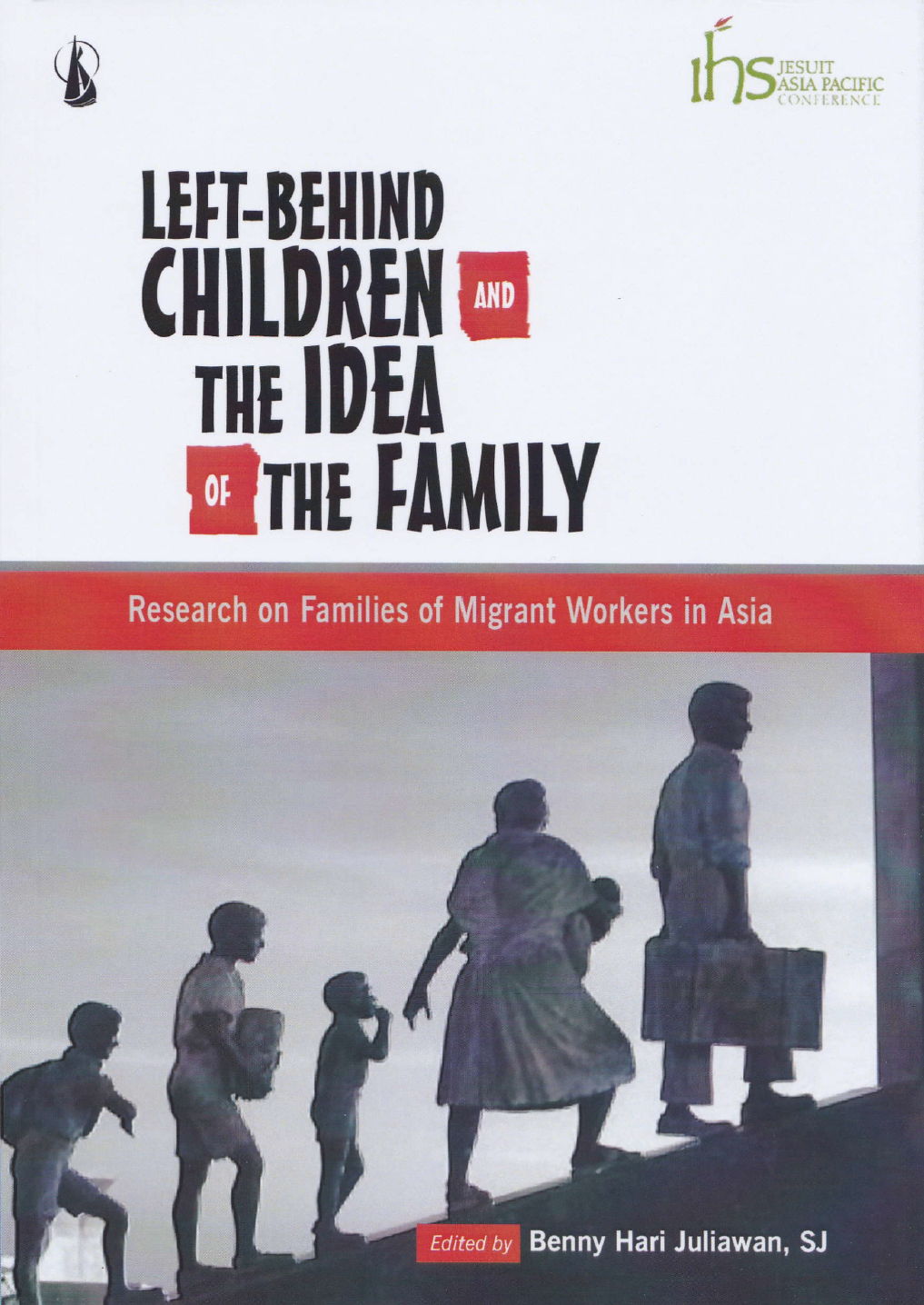
東アジア地域では、若い人たちの移動が盛んになっている。彼ら/彼女らは仕事を求め、自由な国を探している。貧困から逃れて、自分の将来を含め、家族や子どもたちの教育を心配しながら、どんな苦労に遭っても日本、韓国、台湾などへ出稼ぎに来ている。彼らは普段「移民」と呼ばれている。
この「アジア移住」、すなわち、 東アジアの「MIGRATION」の現像を取り扱う“Left-Behind Children and the Idea of the Family”(原文英語、2016年、116頁)という本が昨年末に出版された。
東アジア諸国に拠点を持つイエズス会系の移民ネットワークは、以前からアジア移住問題に関心を持ち、移民労働者と関わりながらその状況についての研究も続けている。2014年からイエズス会は、この新しい移民ネットワークを結成した。現在そのネットワークに、日本も含む7か国が加盟している。
昨年、ネットワークのメンバーの経験をもとに、5か国の研究者が自国の移民たちの現状を取り上げ、本を英語で出版した。この出版物は外国へ出稼ぎに出掛けた両親の生活状況よりは、あとに自国に残された家族や子どもたちの 目で、新鮮な立場から出稼ぎ労働者の状況等を取り上げている。
本のすべての報告は英語。しかし、少しでも日本の読者が理解できるように日本語の付録(25頁)を作り、様々な教育の場でも使いやすくできている。
突然の宮下公園全面封鎖による野宿者強制排除
下川 雅嗣 SJ
イエズス会司祭

2017年3月27日朝、突然、渋谷区宮下公園は高さ約3メートルの鋼板によって全面封鎖されました。
昨年末以降、この公園では小屋を持たない野宿者が多いときで20名以上寝ています。この日も9名ほどの野宿者が段ボールとブルーシートで冷たい雨をしのぎながら寝ているところへ、突然数十名の警備員・警察官がなだれ込み封鎖しました。午前9時からの利用者の入園も認めない、野宿者・利用者に対する事前予告なしの抜き打ち・だまし討ちでした。工事内容の説明もなく、雨がやむまで待ってほしいと要求する声も聞かず、瞬く間に大勢の作業員にフェンスで周囲を囲われてしまいました。
突然の封鎖に抗議し公園内に留まった人たちに会うことを求めた支援者の一人は、警察によって逮捕という形で排除されました。公園内にて、多数の渋谷区職員や警備員に取り囲まれ身動きを止められ、15時間以上にわたって公園内の水飲み場・トイレの使用さえ認められず軟禁された人もいました。
公園内外の野宿者・支援者が一体となって行った、雨がしのげる継続的な寝場所を求める交渉は深夜にも及び、最終的には公園課長が今後の寝場所を渋谷区の公共地にもうけるように他部署と責任をもって交渉すると約束しました。

また、持ち出すことが許されなかった、寝るために必要な毛布などの荷物の受け渡しは深夜1時すぎになりました(朝9時に「荷物はすぐに渡すから」と公園を出された人にとっては、荷物の返還を要求してから12時間以上が経過しています)。
この日、宮下公園を追い出された野宿者たちは、渋谷区庁舎前に移り寝ました。
ところが翌28日午前9時頃に、渋谷区は数時間前の約束がなかったかのように、その場所の工事を始めようとしました。そして、これに抗議した野宿者の一人は逮捕されてしまいました。
その後、上述の2人の逮捕者は、嫌がらせのように拘留延長され約3週間留置されましたが、起訴されることもなく釈放されました(何もしていないので起訴できるはずがありません)。
また、その時追い出された野宿者たちも、本稿執筆時点で、一人も命を失うことなく、ある公共地に一緒に寝ています。
宮下公園は、東京の繁華街である渋谷の街の中にあります。1990年代後半から多くの野宿者が公園内に小屋を作って暮らし、多いときでは130人ほどの野宿者が住んでいました。また、野宿者のための炊き出しや年末年始の越年キャンプなどが行われてきました。
2009年にナイキジャパンと渋谷区が公園の改造を含む命名権の契約を結んだ際は広範な反対運動が行われ、着工は遅れましたが、渋谷区は2010年秋に野宿者を強制的に排除して公園を封鎖しました。
2011年春にニリューアルオープンした時にはフットサルコートやスケートボード、ロッククライミング場などの有料施設が半分を占め、夜間は施錠することになりました。
2015年春には、排除した野宿者に対して渋谷区に損害賠償を求める裁判で渋谷区は敗訴し、その判決にて、渋谷区とナイキの契約は違法であるとされました。本来、渋谷区は裁判の結果を受けて、原状復帰の道義的責任を負うはずなのに、逆に、2015年秋、「三井不動産が3階建てのショッピングモール屋上に宮下公園をつくり17階建てのホテルを併設する計画」(新宮下公園整備事業)を決定しました。しかしながら、この計画は、公園をほぼ商業施設に作り替えるものであり、これを実現するためには、都市計画審議会1にて都市計画を変更せねばならず、またそれ以前に、都市公園法さえ改正注2しないと実現できないようなものでした。
歴史的にみても、宮下公園は野宿者が命をつないできた場所です。また、都市の中にあって、お金を持たなくてもゆっくり過ごせる大切な場所です。しかし、渋谷区とナイキ・三井不動産などの大企業は公園を商業的な場所に変えようとしてきました。彼らにとって、野宿者・貧困者はお金を生み出さない、すなわち『市場価値(Market Values)』がないので、一貫して排除の対象でしかありません。
現在、渋谷では駅周辺をはじめとする「100年の計」と言われる巨大再開発が進み、さらにオリンピックに向けての準備も加わり、いよいよ野宿者たちの夜間眠れる場所が奪われています。一方で、多くの人々が強いられた競争に駆り出される社会構造はより強固になってきているので、新たに野宿に至る人、また再び野宿に戻る人が減ることはありません。そのような状況下で、三井不動産と渋谷区が推進する新宮下公園整備事業は、初動において野宿者の排除を行いました。それは、同事業が公園の持つ人権を擁護する公共性を無視し、企業の利潤追求と商業的な論理に貫かれた暴力的なものであることを象徴的に表しています。
最近、日本では、GDP(国内総生産)を増やすことが国是のように語られ、マスメディアもこれに賛同するような記事ばかりです。GDPさえ増えれば、苦しい人々の生活もよくなるかのように語られています。オリンピックもGDPを大きくするためにはとても重要なものと位置づけられているようです。しかし、GDPは、国内で生産された価値の合計を意味しているだけで、それと人々の生活とは、直結しません。むしろ企業利益と直結します。GDPが増えれば、貧困層にも分配されるという考え方をトリクルダウンと言いますが、この考え方について、教皇フランシスコも使徒的勧告『福音の喜び』で「いまだにそれを支持する人がいるのは信じられない」と嘆いています(54)。今回の事件は、トリクルダウンどころか、貧困者・野宿者を排除することによってGDPを増やす「逆トリクルダウン」の例とも言えます。
今回の事件は、実はロイターなど、海外にはニュースとして発信されましたが、日本のメディアは東京新聞以外ではニュースとして取り上げてくれませんでした。日本社会は、いよいよ、このような貧困者の窮状に関して鈍感になってきているように思います。それでも、国連への諮問資格を持つ海外の団体(国際居住連合)は、渋谷区に対して、4月10日付で「これは重大な国際法上の人権侵害にあたる」との書簡を送ってくれています。
私たちはいつのまにか、『市場価値』がないと価値がない、という感覚に洗脳されてきている気がします。少なくとも、そのような流れしかニュースになりにくく、人々から注目されないようになってきている気がします。この大きな流れの中で、何が福音的で何が非福音的なのか、現実を深く見抜いていき、必要であれば、その大きな非福音的流れを変えていくように働くよう呼びかけられているのではないでしょうか。
※本稿は、渋谷で活動している複数の団体が共同で出した「渋谷区立宮下公園の全面封鎖に対する緊急抗議声明」(2017年3月30日付)をベースに筆者が書き直したものです。
- この渋谷区都市計画審議会は、全面封鎖後の4月7日に行われました。これは筆者も傍聴しましたが、委員から「今回の公園閉鎖は利用者にも区議会にも知らせてない」、「審議会で決める前に公園を封鎖するのは大きな問題だ」、「この計画の内容は違法だ」、「そもそも公園が商業施設になるのは渋谷区にとってよくない」などの反対意見が多数ありました。反対と明確に宣言した委員がいる一方、賛成と明確に言った委員は存在しなかったのに、「おおむね賛成」と委員長の発言で終わる、まさに結果ありきの意味不明の審議会でした。 ↩︎
- ニュースにもなりませんでしたが、2017年4月、第193回国会にて可決され、より一層、民間企業による公園の商業利用が可能になりました。 ↩︎
【新管区長インタビュー】
レンゾ デ ルカ SJ
イエズス会日本管区長

――ご出身はアルゼンチンですね。どんなところ?
私が生まれたラロケという村は、アルゼンチンの中でも割合田舎の農業地帯にある、人口5千人くらいの村でした。こぢんまりとした村なので、色々な人づきあいがあり、私たちは子どもの頃から教会に行くのは当たり前みたいな感じで、生活の一部としての教会でした。まだ昔風の教会の交わりがありました。
――イエズス会の司祭を志したのはなぜ?
ミッションスクールで育てられたということもあって、神父やシスターの姿をよく見ていました。司祭職という選択肢は、子どものときから一つの可能性としてありましたが、中高くらいに入ると、自分が神様から呼ばれているような感じがしました。色々な修道会の神父がミサや召出しについての話をしに学校に来ていたのですが、あるときたまたま来たイエズス会の神父の話を聞いて、その霊性に惹かれました。イグナチオの霊性を知りたい、霊操をしたいと思って、結果的に17歳のとき、高校を出てすぐにイエズス会に入会しました。
――どういった修練期を?
私が住んでいたラロケのあるエントレ・リオス州には、イエズス会は教会も施設も持っていませんでした。なので、修練院と神学院がある、ブエノスアイレス州のサン・ミゲルというところに移りました。
私たちが入会したときには軍事政権はもう終わっていて、民主主義に変わっていました。もちろん、依然行方不明の人が多かったといった問題は色々抱えていましたが。修道会に集まっている人の中にも、家族が迫害したグループに入っている人もいれば、迫害されていたグループの側の人もいました。一般社会の中の色々な傷をもっていて、敵対意識もありました。田舎の方にはゲリラや軍人が来るということがあまりなかったので、私たちはそれほど生で感じることはなかったけれど、その後色々な話を聞かされました。教皇フランシスコが修道院長や管区長だった時代のことも、後で聞くことになりました。
――日本に派遣されることが決まったときには?
私たちは十数人志願したので、最初からそのつもりでしたし、ある意味では願いが叶えられたという気持ちでした。ただし、日本に対して何かイメージを持っていたかというとまったくなく、まるで未知の世界でした。
――1985年に来日して、はじめての日本の印象は?
17歳で田舎から都会に出てきたときのギャップと比べれば、日本に来たときは、思ったよりも違っていないという印象を受けました。ただし、後で振り返ってみると、私たちは結局、修道院から修道院への移動ですから、どっちにしても同じイエズス会で、言葉に困れば誰かがスペイン語や英語を喋れます。そういう意味では、普通の出稼ぎ労働者や外国人客として来る人とは全然違う、恵まれた環境だったので、それほどショックを受けるということはなかったですね、正直。
――司祭に叙階されてからは?
96年に司祭叙階を受けました。最初の赴任地は長崎でした。後に総長になったニコラス神父が管区長だったとき、長崎でキリシタン史をやり続ける人が必要だということで、すでにオリエンテーションが出ていて、神学期の最後の頃から準備をしていました。当時は結城了悟神父がまだ元気で二十六聖人記念館の館長をやっていたので、九州大学の修士課程で歴史の勉強をするチャンスも与えられました。そのうちに交代が必要になり、2004年に私が館長になりました。
――約20年間の長崎生活で印象に残っているのは?
やはり巡礼者たちの心といいましょうか、場所の持っている力というものをよく感じました。私たちはそこに住んでいたので慣れてしまうのですが、はじめて訪れた人や時々外国からもわざわざパウロ三木たちが殉教した場所を見たいとやって来る人もいて、非常に感動するんですね。修学旅行生たち、特にミッションスクールの生徒たちが毎年たくさん来ますが、子どもたちもやはり、ルドビコ茨木などの自分と同じ年齢の子どもたちも殉教したんだということを見ると、大きなショックを受けています。
もう一つ印象に残っているのは、20年の間に、韓国からの巡礼者が劇的に増えたということです。私が長崎に来た頃はまだほとんどいませんでしたが、少しずつ交流ができていって、今ではもう、日本人よりも韓国人の来館者の方が多いかもしれません。ですから、殉教者を通しての交流とか、信仰を中心にして日本と韓国が一致できる部分があるのではないかと思います。互いに色々な歴史があり、ライバル意識や敵対意識がある中で、やはりそれを越える力――この場合は、殉教者たちが「なに人」であるかを問わずにキリストのために命を捧げたという力――があると、自分たちの不満が小さくなっていくように感じます。それを強調することで、二つの国の一致や、もっと交流を深めるための一つの良いしるしとして与えられた恵みを生かしていく必要があるかなと思います。
――教皇フランシスコ(ベルゴリオ神父)はどんな人?
彼は「民の信仰」、信心深い民という言葉をよく使います。神学的な考察とかはあまり知らないし、公教要理も子どものときにしか教育を受けていない、信仰の面でいえばそういった人たちがほとんどですが、その人たちこそ教会を動かしている、教会そのものだということを彼はよく言っていたんですね。
あの時代、アルゼンチンでは教会の勉強や神学は、神父や修道会の人しかやらないようなことがあって、ある意味で差別、つまり教会のことをあまり知らない一般の人たちに口を挟まれたくないという雰囲気があったんですね。それは司教団のレベルでも修道会の中でもそうでした。ホルヘ(ベルゴリオ)神父はその中で最初から、その人たちこそ教会は何であるかという教会の姿を見せている、彼らが私たちの教えを学ぶというよりも、私たちが彼らのあり方とか信じ方に学ぶべきだ、と言っていました。
それで私たちが哲学生・神学生だったときには、毎週どこかに、割合に貧しい人たちのところに行って、子どもたちと一緒に公教要理の勉強をやったりしていました。それによって私たちも少しずつ変化していきました。いくら良い考察を学んだとしても、一般の人たちに分かるように説明できなければ意味がないという感じに。そのためには、この人たちの願いや希望は何なのかということに耳を傾けなければいけません。決まったプログラムではないけれど、一般の民と触れるチャンスを非常に与えてくださったので、結果的に数年間のそうした接触によって、私たちは養われていきました。これはもう、最初から今でもそうで、彼が教皇として今なおとても大事にしている点です。
同時に、やはり勉強はしっかりするようにと、結構厳しかったです。一般の労働者は一日8時間働くのだから、私たちも少なくとも8時間は勉強しないといけない、それが私たちの仕事なんだと、勉強をさぼらないようにいつも言っていました。両方のことを強調して、すごく良いバランスの取れた人だと思います。
◇参考:映画『ローマ法王になる日まで』
――日本の“新”管区長としての今後のビジョンは?
イエズス会の管区長は、一人ひとりの会員と話して、一人ひとりの希望などを聞いてから派遣します。私はまだ始まったばかりなので、4回目のビジタチオ(現場訪問)を終えたところです。会員全体のことを聞いていないと全体を把握できないので、一人前の管区長にはなれないと、やればやるほど感じています。
会員の高齢化の中で、また昔より外国人宣教師も日本人入会者も少なくなっているので、当然ながらどんどん会員は減っています。小さくなっていく中で、何を残すべきかということを識別する必要があります。イエズス会は学校やセンターを色々もっていて、その中で指導していますが、今の日本の教会にとって意味があって、イエズス会にしかやれない仕事とは何なのかということです。私たちが修道会としてやっていたことも、信徒に任せていいものはどんどん任せていくべきだという流れがあります。そのためにはもちろん、信徒の養成も欠かせません。
その意味で、三本の柱があります。一つ目は神学的考察。私たちはこの日本で、より日本人のための神学を築いていくべきです。二つ目は霊性。イグナチオの霊性を指導すべきで、信徒の養成にとっても重要な要素です。そして三つ目は社会使徒職という、社会に対して訴える部分。つまりキリスト教を伝える中で、「社会の中で」やるということです。この三本の柱は、どの機関、どの分野にも当てはまります。大学の中でも教会でも、神学的考察と霊性と社会の次元が必要で、この三つの要素を取り入れていくために何をすればいいか、逆をいえば、その妨げになるものを今後はどんどん手放していくプロセスになります。
社会司牧センターも、もちろん社会使徒職が中心ではありますが、そうした中でも願わくは神学的考察や聖書から見た社会の分析、あるいはイグナチオ的な霊性を取り入れてやっていってほしいと思います。
以前は、召出しは「召命チーム」があるからそこに任せればいいという意識が長いことありました。今はそうではなくて、現場で人々と接する一人ひとりの会員の意識が高まらないといけません。同じように、この三つの要素が、願わくは会員たち――神学生から引退した人まで――のすべてに浸透していけばいいと思っています。非常に「日本的」なことに、それぞれの会員があまりに「専門化」しすぎてしまった中で、この三つの柱をできるだけ統合していく方向です。
【聞き手(文責): 柳川朋毅】
みんな同じ人間!兄弟!仲間さ!
~キリスト者メーデー集会2017~
柳川 朋毅
イエズス会社会司牧センタースタッフ
毎年、メーデーと労働者聖ヨゼフの日(5月1日)の時期に合わせ、「人間らしい生活と労働」を求めて集う「キリスト者メーデー集会」が、今年も4月29日に、東京で開催されました。2017年は「みんな同じ人間!兄弟!仲間さ!」というテーマで、特に移住労働者や有期・非正規雇用労働者のことを二人の講師から学び、労働者の連帯を祈りました。

一人目の講師は、移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)代表理事の鳥井一平さんです。オーバーステイの容認(1980年代)、日系労働者の導入(90年代)などによって、日本は歴史的に移住労働者を受け入れてきました。にもかかわらず、日本政府は「移民政策」という言葉を使うことを避け続け、外国人を労働“者”としてではなく、使い捨て可能な労働“力”として扱ってきました。その最たるものが、「外国人技能実習制度」です。技術移転や国際貢献といった建前とは裏腹に、実態としては目を覆いたくなるような深刻な人権侵害の温床となっています。
そこで鳥井さんは、移民の存在なくしてこの社会は成り立たないのだという事実を直視し、労使対等原則が担保された多民族・多文化共生社会を目指した「まっとうな移民政策」を行うべきだと訴えました。
二人目は、いくつかの大学で非常勤講師や客員研究員を兼任されている仁井田典子さんです。1990年代、フリーターやニートといった言葉が行政でも使われるようになった頃から、若者の雇用問題は、若者本人(個人)の責任であるという風潮が強まりました。法制度にもこうした考えは反映され、個人の責任や負担が増す一方で、労働者は分断されていっています。
そうした中で仁井田さんは、自身も若者、女性、有期・非正規労働者である立場から、コミュニティ・ユニオンの可能性に着目しました。個人加盟の労働組合が繋がりや仲間を見出せる場として機能することで、労働者たちが孤立することなく、個々人が主体的に活動できるようになるというのです。